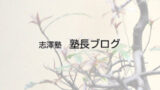先日志澤塾における講座は、私の親友でもあり俳人(帰燕抄という360句にも及ぶ句集を出版したのだからもう俳人と呼ばせていただく)土方公二氏による、俳句鑑賞の仕方について話して頂いた。氏の句集の中からあらかじめ事前に30句を抽出し、それぞれを3種類に分けて丁寧に解説してもらった。私は知らなかったが俳句には《写生句》《取合せ句》《心象句》に分類される。その主な句を列挙してみる。
Ⅰ 写生句
鑑真の海まなかひに夏座敷
揚州の僧鑑真は聖武天皇の招請を受け日本に授戒の法をもたらすため五度の難船と失明の後、七五三年薩摩坊津に上陸した。律宗の開祖。唐招提寺を開く。芭蕉「若葉して御目の雫ぬぐはばや」季語「夏座敷」(夏)。「鑑真の海」は省略表現。「まなかひ」は「まのあたりに」。友人が退職後故郷へ帰って新築した新居へ対する祝句。
Ⅱ 取合せ句
火の痕の残りし瓦すべりひゆ
武蔵国分寺跡吟行。八世紀、天然痘や飢饉を払うため聖武天皇が国分寺六十八寺を全国に建立。その約六百年後に焼失したが、瓦が資料館に残る。(播磨国分寺も同じころ創建)季語「すべりひゆ」(夏)という荒れ地に繁殖する雑草との取合わせ。
Ⅲ 心象句
清明の産屋さざなみあかりかな
季語「清明」(春)は二十四節気の一つ。陽暦では四月五日ごろで「清浄明潔」との意味。「産屋」は記紀の頃からの「産婦の別火」のための小屋である。かつては忌のためであった産屋に清明の清浄さを取合せた娘誕生を祝う心象として詠んだ。
私には読めない字もあるが、それぞれの中から特に印象に残る句を挙げると、先ず写生句から《贄の羽 散る一瞬の 鷹の空》《手を拭いて 母の加わる 月見かな》次に取合せ句から《我が骨は 故山に埋めよ しづり雪》《父母に 永遠の帰省子 稲の花》最後に心象句から《清明の 産屋さざなみ あかりかな》《綿虫と ゐる残照の 消ゆるまで》
 氏は多くは語らないが、京都大学時代や卒業してからの日産自動車勤務での38年、様々な体験があったはずである。その後井上弘美という日本を代表する俳人と出会えたことが今の彼の充実感を醸し出している。
氏は多くは語らないが、京都大学時代や卒業してからの日産自動車勤務での38年、様々な体験があったはずである。その後井上弘美という日本を代表する俳人と出会えたことが今の彼の充実感を醸し出している。
志澤塾最後のゲスト講師にふさわしい講義内容だった。私は好き句道を歩むが大目に見て欲しい。